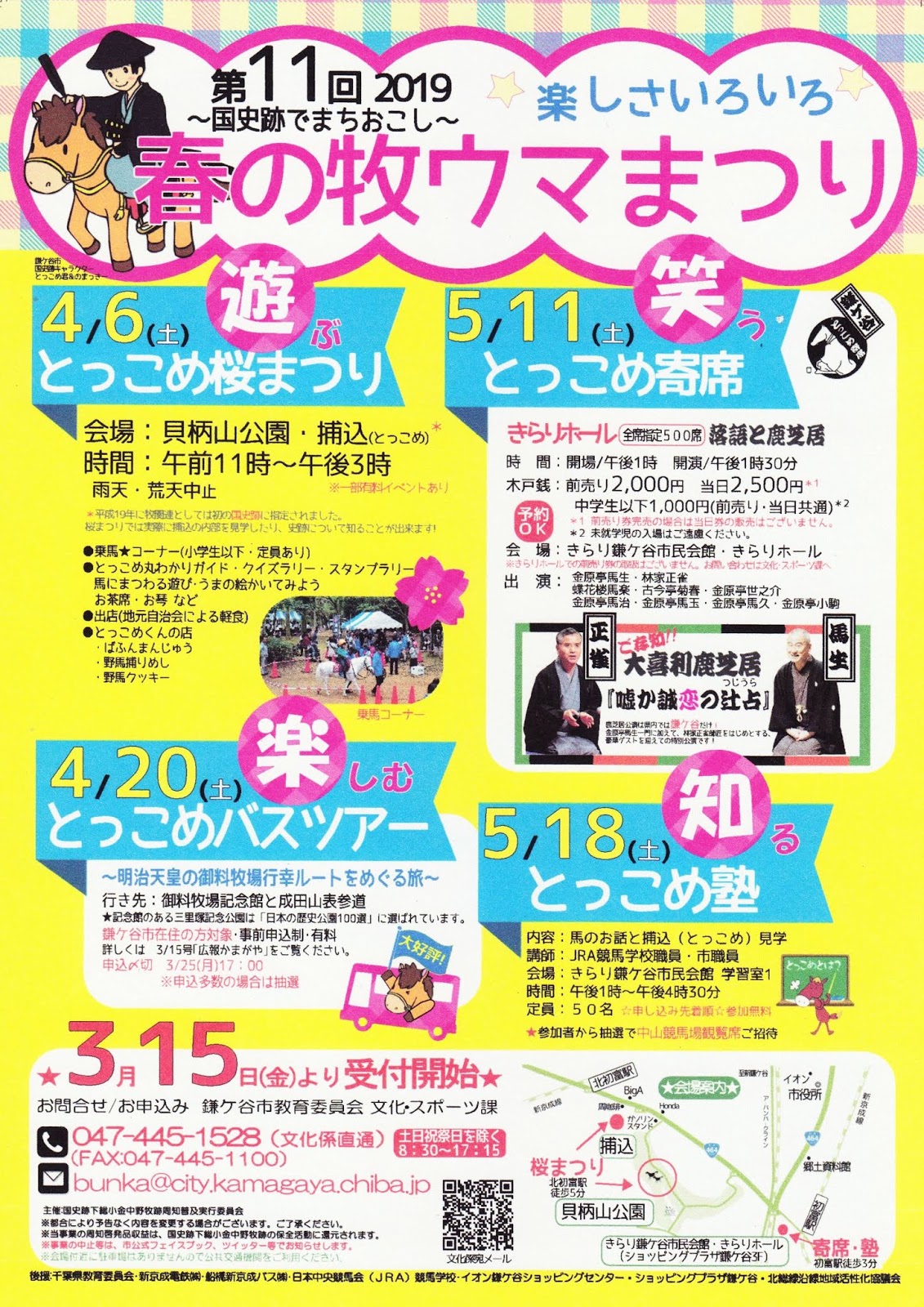彼が終生バックアップし続け、〈その ごみ箱を漁れば交響曲の一曲ぐらいは書ける〉と言わしめた後輩のドヴォルザーク(1841〜1904)にだって負けていないぞ。
そして、完全主義者だった。
未完成遺稿などという つまらないものは、後世に残さなかった。
気に食わぬものは、みな燃やしてしまった。
交響曲だって、全部でたったの4曲。
しかも、それら全てが素晴らしい。
十分ではないか。
これら4つの交響曲は、各季節に当てはめることができると思う。
ブラームスは、私にとって もっとも聞く機会が多い作曲家である。
一曲選べと言われれば、最晩年の作品119『4つの小品』(1892)の第1曲を挙げたい。
少ない音で寂びさびと綴られており、心をわしづかみにされる。
晩年を迎えたブラームスは、ミュールフェルトという優れたクラリネット奏者と出会い、一連の室内楽の名曲を作曲した。
このことが、ブラームスをもう一度ピアノへと立ち帰らせる契機になったのではなかろうか。
ブラームスは、作曲家であるとともに、自身が優れたピアニストだったのだ。